パーキンソン病・運動障害疾患(PMD)センター
| 電話番号 | 042-341-2711 |
|---|---|
| 内線 | ------ |
| 受付時間 | 9:00 |
|---|---|
| 休診日 | 土、日、祝祭日、年末年始 |
診療内容・特色
パーキンソン病・運動障害疾患センター(Parkinson disease & Movement Disorder Center; PMDセンター)では、下記の3つをミッションと考えています。1.パーキンソン病・運動障害疾患の患者さんに国立精神・神経医療研究センター(NCNP)病院及び研究所等NCNPの総力を挙げて、その疾病だけなく、その疾病をもつ一人の人間である患者さん一人ひとりに適切な最高の医療を提供する。
2.パーキンソン病・運動障害疾患の新しい治療法、診断法を開発する。
3.患者さん、ご家族、医療関係者、国民全体にパーキンソン病・運動障害疾患に関して正しい知識をもっていただけるよう、また研究開発にご協力いただけるよう、公開講座、出版物、ITなどを通じて情報を発信する。
主な症状・対象の疾患と外来
対象の疾患と外来
PD(パーキンソン病)専門外来
【医療機関専用・WEB申込不可】
パーキンソン病は運動機能に影響を与える神経変性疾患で、震えや筋肉の硬直、運動の遅れなどの症状を特徴とします。
当外来では、薬物療法、リハビリテーション、外科的治療をご提供いたします。
ヴィアレブ/デュオドーパ専門外来
【医療機関専用・WEB申込不可】
進行したパーキンソン病の症状管理のための治療を行います。
これらの治療法は、持続的な薬物投与によって症状を安定化させることを目的としています。
DBS専門外来
【医療機関専用・WEB申込不可】
DBS(脳深部刺激療法)外来では、パーキンソン病や難治性の振戦、ジストニアなどに対する治療を行います。
DBSは脳内に電極を埋め込んで神経活動を調整する治療法で、患者さんの症状を効果的に管理します。
スタッフ
-
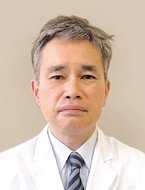
髙尾 昌樹(パーキンソン病・運動障害疾患(PMD)センター) 臨床検査部長、総合内科部長
- 経歴
- 1990年 慶應義塾大学卒業
- 専門分野・資格
- 内科 脳神経内科 神経病理/神経内科専門医 総合内科専門医 日本脳卒中学会専門医 日本認知症学会専門医
-

弓削田 晃弘(パーキンソン病・運動障害疾患(PMD)センター 医長
- 経歴
- 金沢大学 平成13年卒(医学博士)
- 専門分野・資格
- 神経内科専門医 認定内科医 日本定位・機能神経外科学会技術認定医 / 運動障害疾患 脳深部刺激療法 (DBS) 臨床神経生理学
-

向井 洋平(パーキンソン病・運動障害疾患(PMD)センター) 医長
- 経歴
- 徳島大学 平成15年卒(医学博士)
- 専門分野・資格
- 神経内科専門医 総合内科専門医 / 神経変性疾患 運動異常症 (特にジストニア) ボツリヌス治療 神経生理学
-

大平 雅之(パーキンソン病・運動障害疾患(PMD)センター) 医師
- 経歴
- 1999年 慶応義塾大学卒業
- 専門分野・資格
- 脳神経内科/神経内科専門医 総合内科専門医 日本脳卒中学会専門医
1.診療
PMDセンターの診療部は疾患及び病態により以下の5つのグループがあります。それぞれのグループはたがいに密接に関連、協力していますが、特に嚥下障害グループはすべての疾患グループにかかわっています。
パーキンソン病・パーキンソン症候群グループ
パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症(特に線条体黒質変性症;MSA-P)などが対象です。運動症状のみならず、抑うつ、不安、睡眠障害や、腰曲がりなどの姿勢障害などにも対応しています。初期には、正確な診断、適切な薬の種類と量の選択、リハビリテーション、疾患の正しい知識を得ていただくことが重要です。短期入院により、適切な薬の量を決定するために必要に応じてL-dopa の血中濃度と症状の変化を評価するL-dopa testや、ご自宅でのリハビリテーションの指導、疾患を正しく理解していただくための教育などを行っています。
その後も、疾患の状態に合わせ、経過の評価とそれに合わせてその時必要な医療の選択、リハビリテーション指導などのために、外来診療とともに、定期的な短期評価入院をお勧めしています。特にパーキンソン病でウエアリングオフ現象や不随意運動が出現している方にはL-dopa testにて、薬の効果と症状との関連を評価し、薬剤調整を適切に進めることができます。
また、パーキンソン病認定薬剤師の認定資格を付与するためのトレーニングや評価を行い、パーキンソン病の薬物治療に精通した薬剤師の育成に努めています。
パーキンソン病や不随意運動症では必要に応じて、脳外科的治療(脳深部刺激術など)も行い、術後の刺激調節や薬剤調整を脳神経外科と脳神経内科が共同で行っています。
睡眠障害や不安のためにパーキンソン症状が悪く見えることも多いので、これに対しても睡眠障害センターや認知行動療法センターと連携した専門的治療も進めています。
レビー小体型認知症グループ
パーキンソン症状と共に認知症状、幻覚、妄想などの精神症状が出現しやすいため、脳神経内科と精神科の協力が不可欠です。患者さん及びご家族のQOLの向上をめざし、適切な治療を選択しています。小脳失調症・ハンチントン病グループ
多系統萎縮症などの孤発性の小脳失調症とともに、マチャド・ジョセフ病など遺伝性の脊髄小脳変性症、ハンチントン病などが対象です。小脳症状、自律神経症状、その他いろいろな症状の組み合わせがあるので、正確な診断とともに、その時々の症状を評価したうえで適切な薬剤の選択やリハビリテーション等とともに、社会資源の活用のご紹介も含め、一人ひとりの状態に合わせた医療を提供いたします。マチャド・ジョセフ病、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)、ハンチントン病などの遺伝性疾患では、遺伝相談が大変重要です。診療科と遺伝カウンセリング室が一体となって対応しています。
ジストニアグループ
痙性斜頸、眼瞼スパスムなどへのボツリヌス治療の他、パーキンソン病グループと共同して、パーキンソン病関連疾患の姿勢異常(腰曲がり、頸下がりなど)に対する治療を行っています。ジストニアは精神的ストレスの影響を受けやすいので、認知行動療法(CBT)も進めています。嚥下障害グループ
パーキンソン病を始めとする運動障害疾患では、嚥下障害は大変重要です。このグループではNST(栄養サポートチーム)と協力して、嚥下障害の評価とともに、嚥下指導、食形態の選択、さらに必要なら胃ろうなども含め、ご本人、ご家族のご希望を伺いながら、最も安全かつ適切に栄養が摂取できるように工夫しています。2.臨床研究
現在、当センターでは以下のような臨床研究を進めています。1.パーキンソン病の薬物動態に関する研究
2.パーキンソン病の不安、抑うつに対する認知行動療法(CBT)の開発
3.パーキンソン病、レビー小体型認知症の幻覚等精神症状の実態とその治療についての研究
4.パーキンソン病、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺の早期診断、経過評価のためのバイオマーカー検索についての研究
5.パーキンソン病のオーダーメイド医療確立のための研究
6.パーキンソン病の自然歴に関する前向きコホート研究
7.パーキンソン病・不随意運動における脳深部刺激療法の刺激条件最適化に関する研究
8.パーキンソン病発症予防のための運動症状発症前biomarkerの探索研究
PMDセンターではパーキンソン病の治験・臨床研究を進めるため生前同意に基づくブレインバンク(https://brain-bank.ncnp.go.jp/)の推進にも力をいれております。






